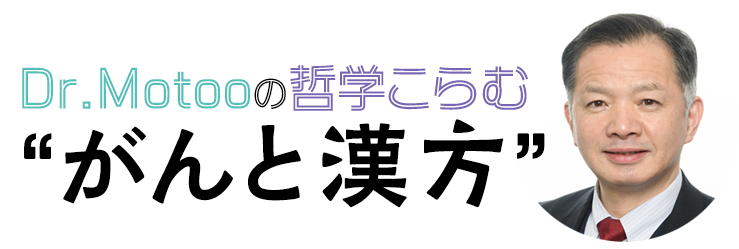vol.13 混合病態にこそ漢方
がん薬物療法を受ける患者さんには、口腔粘膜炎、悪心・嘔吐、便通異常など複数の症状が同時多発あるいは波状的に襲ってきます。その患者さんにとっては「混合病態」になっています。しかし、実際には、各症状に1対1対応することになりますが、そのような支持療法で一気に薬剤数が増えてポリファーマシー(多剤併用)になってしまいます。
一方、漢方診療では、患者さん全体を漢方医学的にとらえて、漢方医学的な診断である「証(しょう)」を決定します。証が決まると処方が決まることを「方証相対(ほうしょうそうたい)」と呼びます。このようにして決定された漢方処方は、多成分系薬剤であり、さまざまな作用を持つ生薬の有機的集合体ですので、一つの処方で複数の症状に対応することが可能です。
臨床現場では、目の前の患者さんの症状に、いわば対症療法的に多くの薬剤を処方することが多いのですが、漢方医学的に患者さんを診て、いわゆる西洋医学だけでは見えない姿が見えるのは良いことではないでしょうか。しかも漢方を処方できるのですから、臨床医にとってはあらたな治療オプションを手に入れることになります。
上記の話はがん薬物療法という特殊な状況のことについてですが、多くの臨床医学分野でも混合病態のような場面は必ずあると思います。患者さんが訴える症状には複数の因子が関与していることが多く、表面に出ている症状の奥に存在する病態は何かをよりわかりやすく理解できる手段があればいいですね。漢方がその一翼を担っている可能性が高く、今後さらに解明されていくことに期待したいです。
vol.12 早し良し
がんサポーティブケアの米国国立がん研究所の定義は、「がん患者が治療を受ける際の種々の副作用を軽減し、さらに心身・社会的・スピリチュアルな問題にできるだけ早期に対応して、各治療がその効果を最大限に発揮できるようにするためのすべての医療行為を指す」となっています。
この「できるだけ早期に対応する」というフレーズから私は「未病を治す東洋医学」を連想しました。とくにがん薬物療法の副作用は重症になってから対処したのでは、ほとんど効果はありません。できるだけ早期に副作用の発現を予知して、可能なあらゆる手を打つべきです。とくに現代西洋医学で対処法のない副作用、たとえば末梢神経障害(手足のしびれ・痛み)は、もともと有効な対処法のない症状ですが、神経障害性疼痛として、その治療薬が使われることが多いです。ただし、眠気やふらつきなどの副作用が出ることがあります。一方、漢方製剤の牛車腎気丸(ごしゃじんきがん)には「しびれ」の効能・効果があり、糖尿病性末梢神経障害などにも使われてきました。現在でもがん薬物療法で頻用されるパクリタキセルは末梢神経障害を起こしやすい抗がん剤です。
これまでにパクリタキセルによる末梢神経障害に対する牛車腎気丸のいくつかのランダム化比較試験が発表されています。最近では薬物療法の開始1週間前から牛車腎気丸を開始すると末梢神経障害が軽減し、終了後6ヶ月時点での末梢神経障害の残存率が減ることがわかりました。
このように早く漢方を使うことで重篤な副作用の軽減、重篤化予防などが得られる可能性が科学的に証明される時代になりました。ただし、予防的に漢方製剤を使うことは保険診療では原則できないので、たとえば牛車腎気丸であれば、腰痛・頻尿・冷え症などの、効能・効果に挙げられている症状がないかを問診によって確認する必要があります。これらの一つでもあれば牛車腎気丸を使えます。実際には担当医にご相談下さい。「早し良し」という言葉がありますが、漢方診療ではとくにその重要性が再認識されます。
vol.11 こころにも届く漢方
がん医療では、身体症状の緩和が主になる場合が多いですが、精神症状(心 [こころ]の症状)は身体症状と並んでまさに両輪とも言える重要な問題です。漢方医学には「心身一如(しんしんいちにょ)」という言葉があります。こころとからだは切っても切れない関係であり、こころがからだに、からだがこころに影響します。ある問題に悩んでいると食欲がなくなったり、痛みがつらいと気分が落ち込みます。漢方医学で扱う「気血水(きけつすい)」のうち、物質的な血と水は、気がないと動きません。漢方がこころの問題にも対応できることを知らない人もいることでしょう。漢方薬の他に鍼灸もこころに届きます。
こころの問題には、陽性症状として怒りやイライラがあり、陰性症状としてうつや不眠などがあります。漢方ではこれらの症状に対する処方がいろいろとあります。
陽性症状に用いられる漢方処方では抑肝散(よくかんさん)が有名です。ここでの「肝」は肝臓ではなく、漢方では感情の調節中枢を指します。元来は乳幼児のむずかり・夜泣きの薬でしたが、その後、成人に応用され、怒りや興奮に用いられてきました。抑肝散が乳がん患者の手術前後の不安感の軽減に有効であることがランダム化比較試験で検証されています。さらに、応用処方としては、胃腸虚弱には抑肝散加陳皮半夏(よくかんさんかちんぴはんげ)、多愁訴で月経周期に関連すれば加味逍遙散(かみしょうようさん)、発作的な感情の高ぶりには甘麦大棗湯(かんばくたいそうとう)(頓服)、体力があり、のぼせや熱感を自覚する場合には黄連解毒湯(おうれんげどくとう)などがあります。
一方、陰性症状については、不安・うつには半夏厚朴湯(はんげこうぼくとうう)、身体的疲労や貧血があれば加味帰脾湯(かみきひとう)が基本処方です。さらに応用処方として、うつ症状が主であれば香蘇散(こうそさん)、疲れているのに眠れない場合は酸棗仁湯(さんそうにんとうう)などが用いられます。
このように「心にも届く漢方」があることを知って頂き、からだとこころのバランスを取りながら、毎日の生活を少しでも快適に過ごしたいものです。