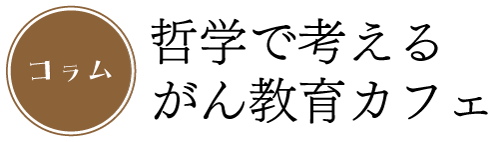Vol.18 【つまるところ、コミュニケーション!】
一般社団法人がん哲学外来(通称「がん哲学外来」)は、がん教育の学びを哲学で考える「がん哲学の視点からのがん教育」(「哲学で考えるがん教育カフェ」改称)を毎月開催しています。カフェは既に各地でがん教育に携わる方々にご参加いただき、参加者と共に話し合う場で、がん教育の重要性が問われる中、外部講師を育てサポートすることを目的としています。
2025年11月開催のがん教育カフェは次の通りでした。
〇2025年11月8日(土) 16時~17時(WEB開催)
講師: 北郷秀樹さん(がん治療相談家)
講座: 「相談の一歩をもっと身近に」
世の中は「令和のクマ騒動」問題が深刻化し、ついに自衛隊が出動することになりました。クマは山奥にいるものと思われていた時代は、もう過去ということでしょうか。私たちの日常にクマが入り込んできたら、とても安心して過ごせるとは思えません……。
11月最初の土曜日に開催されたカフェでは、「対話が大切シリーズ」の北郷秀樹さんに登場いただきました。
病院でがん治療を受けようと決めた場合、治療をうける病院や主治医を選び、治療内容を確認・納得した上で治療がスタートします。長いつきあいになりますので、当然ですが主治医との良好な関係を構築することがなにより大事となります。特に知名度の高い病院に勤務する勤務医は、一般的に多忙をきわめていますので、患者一人に多くの時間を割くことはできない現状です。それでも、わからないことや困っていることがあったら相談する先は主治医となります。しかし、がん患者の方々が十分に主治医に相談できているかとなると疑問が残ります……。
全国のがん拠点病院には「がん支援センター」が設置されていますが、実際に訪れたり相談を受けたりしたことはありますか? 実は、せっかく設置されているにもかかわらず、あまり活用されていないのが現状なのです。もちろん、自身のがん治療について不安や困ったことがなければ活用する必要はありません。この日は、このセンターがあまり利用されていないことをあげ、その現状の背景を探り解決策について意見交換を行いました。
2人に1人ががんに罹患する時代、がんが日常に入り込んでくる確率はとても高くなります。がんとの共生のためには、早くからがんについて学び慣れることが求められます。つまるところ、コミュニケーション!といえるでしょう。
今回がシリーズ4回目となる本講座の詳細は、がん哲学外来HP掲載の北郷さんご自身のコラムがアップされていますので、是非アクセスしてください。
★北郷さんのコラム「1人1人の生き方カフェ」
https://gantetsugaku.org/cafecolumn-ikikata/
※ 次回は、2025年12月6日(土)16時~17時開催です。