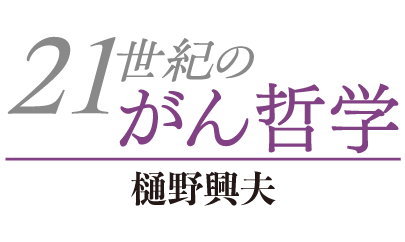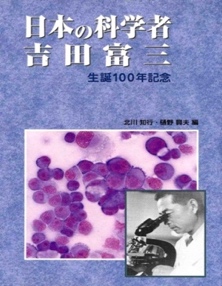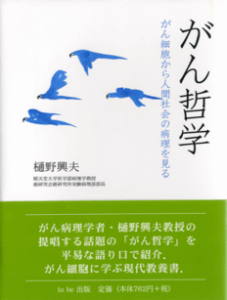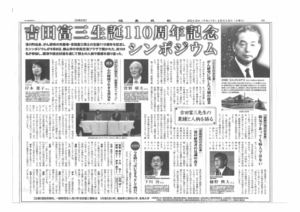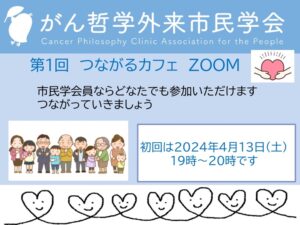第87回 『居場所の重要性』 〜 がん細胞から人間社会の病理を見る 〜
2025年8月26日は、『福島県立医科大学附属病院がん相談支援センター』で2009年スタートした『吉田富三(1903-1973)記念福島がん哲学外来』に赴く。【福島県出身の世界的病理学者 吉田富三博士を記念して、吉田博士の孫弟子 樋野興夫先生と『福島がん哲学外来』を開設いたしました。 患者さんの思いや日常生活の悩みを受け止め、じっくりと対話する“心の診療室”です。 がんにまつわる悩み・不安を持って生きる患者さんと そのご家族の受診をお勧めします。】と謳われている。 ただただ感謝である。
『吉田富三記念 がん哲学外来』は、福島県出身で『吉田肉腫』&『腹水肝癌』の発見などで世界的に知られ、文化勲章を受けた福島県出身の病理学者:吉田富三を記念して、2009年に福島県立医科大学で開設された。 筆者は、医師になり、癌研究会癌研究所の病理部に入った。 病理学者であり当時の癌研究所所長であった菅野晴夫先生(1925-2016)の恩師である吉田富三との『邂逅』に繋がった。 菅野晴夫先生とは、【2003年『日本病理学会』と『日本癌学会』で『吉田富三生誕100周年記念事業』(添付)】を行う機会が与えられた。 必然的に『がん哲学 = 生物学+人間学』、さらに 2008年『陣営の外 = がん哲学外来』(添付)へと展開した。
吉田富三は、『医学者としてのみならず、癌という病気を通じて社会の原理まで言及す言葉』を多数残している。『癌細胞で起こることは、人間社会でも起こる』を学び、2004年『がん哲学 〜 がん細胞から人間社会の病理を見る 〜』(to be出版)(添付)を出版するという時を与えられた。 2013年には『吉田富三生誕110周年記念』を企画され、新聞記事が大きく掲載された(添付)。 2019年『吉田富三記念福島県立医科大学がん哲学外来10周年記念講演会』も企画された。 『居場所の重要性』を痛感する日々である。
第86回 『多様なニーズに対応する』 〜 つながる社会構築 〜
2025年8月18日『2025年度第1回Lynch症候群委員会』に、アドバイザーとしてZoom ミーティングに参加した。順天堂大学医学部病理・腫瘍学教授時代、2014年『リンチ症候群研究会』が設立され、筆者は代表を仰せつかり【リンチ症候群研究会設立の趣旨 〜 今後の展望と期待 〜】を記述したものである。
【近年、遺伝性腫瘍に関する注目度が高まり、一般市民にも知られるようになってきており、様々な分野の医療従事者も、その対応を求められつつある。―― リンチ症候群は、『ミスマッチ修復遺伝子の生殖細胞系列変異を原因とする常染色体優性遺伝性疾患である』と定義され、―― 遺伝に関する指針やガイドラインに沿った検査の実施が必要であると考えられる。―― 各科臨床医・臨床遺伝専門医・病理医が連携を取り、院内体制の構築を検討する必要がある。――『リンチ症候群研究会』では、リンチ症候群の概要とその診療に関連する情報を提供したいと考えている。】と述べた。
『リンチ症候群研究会の3つの使命』
1)学問的、科学的な責任で、病気を診断・治療する
2) 人間的な責任で、手をさしのべる
3) 病気(遺伝病)も単なる個性である社会構築
【『遺伝病も単なる個性である』 & 『病気であっても病人ではない』の社会構築】は、人類の進むべき方向であろう!! まさに、【多様なニーズに対応する『医療人材(プロフェショナル)養成』】の時代的到来であろう!
その後、筆者は代表を務める『がん哲学外来市民学会』(Cancer Philosophy Clinic Association for the People:2011年設立)の『第17回つながるカフェ』(事務局の嶋田弥生氏の司会)(初回は2024年4月13日:添付)に参加した。【がん哲学外来カフェ『赤い屋根』】(大阪府)の発表を拝聴した。 大いに感動した。