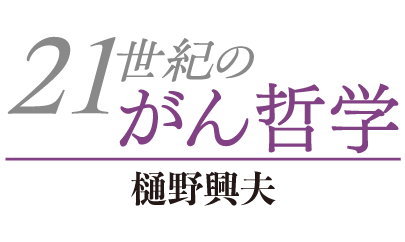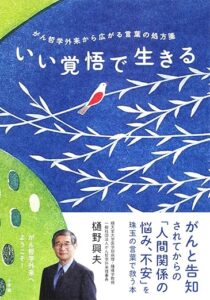第81回 『いい覚悟で生きる』 〜 『言葉の処方箋 & 対話の場』 〜
2025年7月20日『横浜がん哲学外来』(代表・担当者:内田由美子氏)のメンバーの三国浩晃氏から【2026年2月14日(土)に横浜がん哲学外来・カフェ19周年記念シンポジウムを絶賛企画しております。 一昨日の横浜のメンバーは、内田由美子さん、西田千鶴美さん、末永佑仁さん、秋月隼人さん、三国浩晃で、参加者と一緒に樋野先生の『いい覚悟で生きる』(2014年初版) (添付)を 西田千鶴美さんが音読し、格調高いカフェになったのではと思います。】との心温まる励ましの連絡を頂いた。『いい覚悟で生きる』のHPには、下記が紹介されている
『がん哲学外来』提唱者が贈る言葉の処方箋
【がんになっても、人生は続く。 がんになってから、輝く人生だってある。 がんと告知されてから患者さんが心に抱えることは、『病気、治療、死に対する不安が3分の1で、あとは人間関係の悩みが実はいちばん多い。 家族、職場、医師……それまでなんとも思わなかった周囲の言動に反応して心が傷つくのです』と、『がん哲学外来』の提唱者で発がん病理学者の著者・樋野興夫先生は言います。『がん哲学外来』とは、多忙な医療現場と患者さんの『隙間を埋める』べく予約制・無料で開設された、今もっとも注目を集める『対話の場』です。約60分、著者はがん患者やその家族とお茶を飲みながら、不安や精神的苦痛を直に聞いて解消できる道を一緒に探します。 そして、どんな境遇にあっても『人はいかにして生きるか』という人生の基軸となるような『言葉の処方箋』を贈っています。 その数は延べ約3000人にも及びます。 本書は、がん哲学外来の『言葉の処方箋』を初めてまとめた待望の一冊。 著者自身が影響を受けた新渡戸稲造や内村鑑三、病理学の師である吉田富三ら偉人たちの語り継がれる金言から、哲学的なのにユーモアあふれる一言まで、読めばくじけそうな心が元気になる、人生に『いい覚悟』を持って生きるための言葉にあふれています。】
第80回 『人間の探求』 〜 逆境に立ち向かう言葉 〜
2025年7月17日 筆者は新渡戸稲造記念センター(中野区)から東京女子大学(杉並区)の評議員会に出席する。 7月19日は、早稲田大学エクステンションセンター(早稲田校 新宿区)での講座『がんと生きる哲学』に赴く。 本講座(全6回)は【『ジャンル 人間の探求:テキスト:樋野興夫『新渡戸稲造 壁を破る言葉: 逆境に立ち向かう者へ40のメッセージ』(三笠書房)】である。
【講義概要:『がん哲学』とは生きることの根源的な意味を考えようとする患者と、がんの発生と成長に哲学的な意味を見出そうとする医師との対話から生まれました。 病理学者として科学としての癌学には哲学的な考え方を取り入れていく領域があるとの立場に立ち『がん哲学』を提唱しています。 日本人の半分ががんになる時代、好むと好まざるとにかかわらず多くの人が がんと一緒に生きる方法を見つけなければなりません。 本講座ではテキストの読みあわせと解説をしつつ受講者との対話を中心に講義をすすめます。 がんとともに生きる患者さん、家族や身近に患者がいる人、医療従事者等、患者に寄りそいたいと思う方すべてが対象です。参考図書として『なぜ、こんな目にあわなければならないのか がん病理学者が読む聖書「ヨブ記」』樋野興夫著(いのちのことば社)をお読みいただくと、より理解が深まります。】と掲載されている。 大いに感動した。
その後は、【がん哲学外来東中野メディカルカフェ『ひとりで悩まず話してください』(東中野キングス・ガーデン)開設10周年記念講演『楕円形のこころ』&面談】である(添付)。【心を交わす対話の場として開かれた東中野メディカルカフェも、開設10周年を迎えました。 今回は、記念として樋野先生のお話しを聞き、相談も受け付けます。 そしていつものカフェタイム。 病気のこと、家族や友人あるいは先生とのこと、お勤めのこと・・、ご本人はもちろんそのご家族、ご友人、どなたでも共に参加していただけます。】と紹介されている。 感激した。