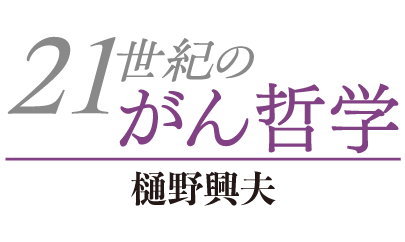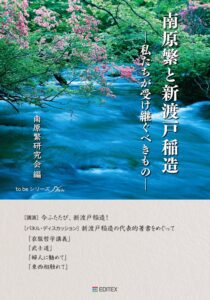第92回 『一筋の光』 〜 『受け継くべきもの』 〜
2025年9月18日 筆者は順天堂大学に寄って、新渡戸稲造記念センター長を仰せつかっている新渡戸記念中野総合病院での倫理委員会に出席した。 皆様の真摯な質疑応答の姿勢には、大変勉強になった。『持続的な向上心の基本』であろう!まさに、『「名誉」とは 境遇から生じるものではなく、自己の役割を まっとうすることにある』(新渡戸稲造1862−1933)の復学である。
その後、Zoom『南原繁研究会(第248回)』に参加した。テーマは、【諸報告 & シンポジウム文献紹介 & シンポジウムパネリストの構想発表】であった。 純度の高い専門性のある発表には、大いに感動した。 筆者は、2004年にスタートした南原繁研究会 【初代代表、鴨下重彦 先生(1934-2011、東京大学名誉教授、国立国際医療センター名誉総長)、第2代代表、加藤 節 先生(成蹊大学名誉教授)】の3代目の代表を、2019年 南原繁(1889-1974)生誕130周年を祝し、仰せつかった。『21世紀の懸け橋/受け継くべきもの』を実感する (添付)。
南原繁は、内村鑑三(1861-1930)と新渡戸稲造から大きな影響を受けた。 南原繁は新渡戸稲造校長時代の一高で学び、影響を受けた。 一高時代、南原繁は『聖書之研究』を読み始め、東大法学部に入学後、内村鑑三の聖書講義に出席するようになった。 『南原繁―>新渡戸稲造―>内村鑑三』である。 筆者は、南原繁が東大総長時代の法学部と医学部の学生であった二人の恩師から、南原繁の風貌、人となりを直接うかがうことが出来た。 南原繁は、『高度な専門知識と幅広い教養』を兼ね備え『視野狭窄にならず、複眼の思考を持ち、教養を深め、時代を読む
具眼の士』と、教わったものである。『時代を動かすリーダーの清々しい胆力』としての『人間の知恵と洞察とともに、自由にして勇気ある行動』(南原繁著の『新渡戸稲造先生』より)という文章が思い出される今日この頃である。
複雑な現代社会・混沌の中での『一筋の光』を学習する日々でもある。
第91回 『生きること、寄りそうこと』 〜 『人生の根幹を追求する』 〜
2025年9月12日筆者は、病理医として病理組織診断業務を担当した。【『病理学』は『形態』&『起源』&『進展』などを追求する学問分野である。『病理組織診断』は『風貌を診て、心まで読む = 人生の根幹を追求する』でもある。『顕微鏡観察』は『細胞の病理と人間社会の病理 = 生物学の法則+人間学の法則】である。『病理学者』が『がん哲学外来』を創設出来たのは ここにあろう! 筆者は、2008年1月順天堂大学の病院の診察室で、無料の『がん哲学外来』を始めた。 そして、病院外で『がん哲学外来・カフェ』を開始する機会が与えられた。
筆者は、アメリカ合衆国のペンシルベニア州のフィラデルフィア(Philadelphia)のFox Chase Cancer CenterのKnudson博士(1922-2016)の下で『遺伝性腫瘍』を学んだ(1989-1991)。 そして、『癌研究所所長:菅野晴夫(1925-2016)先生』に癌研究所実験病理部部長(1991-2004)に呼ばれ帰国した。 原田明夫(1939-2017)検事総長とは、2000年に『新渡戸稲造(1862-1933)武士道100周年記念シンポ』、さらに『新渡戸稲造生誕140年』(2002年)、『新渡戸稲造没後70年』(2003年)、順天堂大学教授に就任(2003年)し2004年には、国連大学で『新渡戸稲造 5000円札さようならシンポ』を企画したのが 走馬灯のように駆け巡って来た。
9月13日は【お茶の水メディカル・カフェ in お茶の水クリスチャン・センター(OCC)】に参上する。 4組(5人)の個人面談の予約もあるとのことである。 想えば、筆者は、『順天堂大学医学部 病理・腫瘍学教授』時代の 2012年5月26日にOCCでの第1回『お茶の水(OCC)メディカル・カフェ』に赴いたものである。東日本大震災の2011年に創設準備がなされ、2012年に当時OCC副理事長であった今は亡き榊原寛先生が『お茶の水(OCC)メディカル・カフェ』を始められた。開設記念は【精神科医であり金城学院学院長の柏木哲夫先生】による講演『生きること、寄りそうこと』で、会場は満席となった。