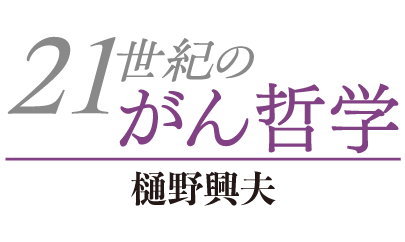第83回 逆境に立ち向かう 〜 無頓着ほどに 賢く生き抜く勇気 〜
2025年8月1日 アメリカ合衆国ミシガン州のGrand Rapids空港からDetroit空港を経由して、羽田空港に帰国した。 8月2日は、早稲田大学エクステンションセンター(早稲田校)での講座【『がんと生きる哲学』〜『ジャンル 人間の探求:テキスト:樋野興夫著『新渡戸稲造(1862-1933)(添付)壁を破る言葉:逆境に立ち向かう者へ40のメッセージ』(三笠書房)】を担当した。 下記を受講者に音読して頂きながら進めた。
1章12節『礼節を持って賢く生き抜く』:他人を尊敬する念は、誰の心中にも必ず潜んでいて、また少し注意すれば、どんな人に対しても、必ず尊敬すべき理由を発見し得るものである。 いやしくも自らを重んじる人は、必ず他人を尊敬する。 もしその念がない人があるとすれば、その人に自重心がないという欠陥を自白するようなものである。『世渡りの道』
2章13節『立ち止まることも勇気である』:勇気を修養する人は、進むほうの勇ばかりでなく、退しりぞいて守るほうの沈勇もまた養うように心がけなければならない。 両者がそろってこそ、真の勇気が得られる。『修養』
2章14節『〝無頓着〞ほど強いものはない』:青年はその特性としてシンプル(淡白)でなければならない。 自然に従い、あけっぱなしで、すねたところがなく、すらすらとして、少しのひがみもないことが必要だ。 いわば心がシンプルなのである。 真の青年は、名誉とか立身とか、つまらぬ小欲がない。 もし欲があるとすれば、それは大欲である。 したがって人に追従をいってご機嫌を取ろうともしなければ、また秘密にすることもないから、なんらわだかまることがない。『修養』
その後、国立がん研究センター築地キャンパスでの【Japan Cancer Forum 2025】に向かった。 『個人面談』の機会も与えられた。【『アルプスの少女ハイジ』:喜んで無邪気に 小さなことに大きな愛を込める】(添付)の復学である。
第82回 『顔を合わせて話し会う』 〜 『心を見る』 〜
025年7月27日午前『KBF in CAJ』に出席した。『がん哲学外来・カフェ』の理念である『顔を合わせて話し会いましょう』(ヨハネの手紙第3 14節)&『人はうわべを見るが、主は心を見る』(サムエル記1 16章7節)が鮮明に想い出された。
午後は、2008年から始めている『東久留米がん哲学外来・カフェ』(CAJに於いて)に赴いた。 初めて参加された方もおられた。 筆者は、個人面談の時も与えれた。 参加者、スタッフの皆様の真摯なる姿には、ただただ感謝である。
その後 2007年から始めている読書会(東久留米駅東口『イースト サイド カフェ & ダイニング』)に出席した。 今回の読書会の箇所は、内村鑑三(1861-1930)著『代表的日本人』の【日蓮上人 仏僧 8節 人物評】であった。 【『目白がん哲学外来カフェ』代表:森尚子氏】が音読を担当された。 大いに感動した。 筆者の著書『新渡戸稲造(1862-1933)壁を破る言葉: 逆境に立ち向かう者へ40のメッセージ』(三笠書房)】の1章【逆境にどう立ち向かうか】の10節『順境のときこそ自分を戒める 〜 順境にいるときの「五つの落とし穴」〜』(下記)でも話が盛り上がった。
『五つの落とし穴』
1. 順境にある人は傲慢になりやすい
2. 順境にある人は怠けやすい
3. 順境にある人は恩を忘れやすい
4. 順境に慣れてしまうと不平不満が多くなる
5. 順境に慣れてしまうと調子に乗りやすい
終了後、隣のインド料理店ルチラで、読書会に参加された方と、夕食の時をもった。 大変有意義は貴重な時となった。 継続の大切さが身に沁みる日々である。