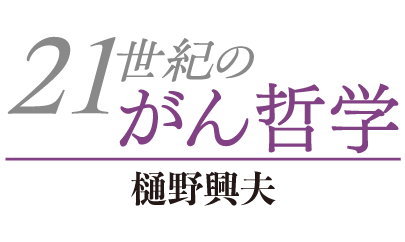第126回 役割意識と使命感の自覚 〜 『人生は限りなきの 播蒔きなり』〜
2026年2月21日 筆者が理事長を務める【がん哲学外来市民学会】の『第23回つながるカフェ』Zoom ミーティングに参加した。『つながるカフェ』の事務局は【安藤潔(事務局長)、市村雅昭、片桐考子、丸山範子、森尚子、嶋田弥生】である。 嶋田弥生氏のユーモア溢れる名司会で進行された。今回のスピーカーは長野県佐久市の『ひとときカフェ』 の皆様であった。 まさに 『役割意識と使命感の自覚』の実践である!
『第1回がん哲学外来コーディネーター養成講座』(2011年12月17日、18日)が長野県佐久市で開催され、『佐久宣言』(2011年12月18日)が採択されるに至った。
1)『がん哲学外来市民学会』(Cancer Philosophy Clinic Association for the People) の設立
2)『がん哲学外来コーディネーター養成講座』修了証の発行
【『がん哲学外来市民学会』は『筆者は代表、顧問:柏木哲夫先生(金城学院大学学長/淀川キリスト教病院名誉ホスピス長)・門田守人先生(厚生労働省がん対策推進協議会会長/がん研究会有明病院病院長)・垣添忠生先生(日本対がん協会会長/元国立がんセンター総長)』】でスタートした。『歴史的な船出』であった。 第1回『がん哲学外来市民学会』総会は、『農村医学』の発祥の地・『医療の民主化』を目指す『佐久市』で開催され、まさに、『救済の客体から解放の主体へ』の『市民の為の学会』であった。第1回『がん哲学外来市民学会』(2012年9月23日:佐久勤労者福祉センター)は、筆者が大会長を仰せつかり、長野県、佐久市、日本医師会、公益財団法人日本対がん協会、新聞社、テレビ局などの多数の『後援』も得られた。
思えば『がん哲学』提唱(2001年)—>『がん哲学』出版(2004年)—>『がん哲学外来』開設(2008年)—>『がん哲学外来研修センター』開設(2011年)—>『がん哲学外来コーディネーター養成講座』開催(2011年)−>『がん哲学外来市民学会』設立(2011年)の道のりであった。『人生は限りなきの 播蒔きなり、発芽も収穫も 天意にあり』(新渡戸稲造:1862−1933)を実感する日々である。
第125回 『いい覚悟で生きる』 〜 将来を見据えた『先見性』〜
2026年2月14日『日本 Medical Village 学会』理事長として、横浜開港記念館での【『横浜がん哲学外来18周年&第8回『日本Medical Village 学会』〜いい覚悟で生きる〜』】 (大会長 内田由美子 和み訪問看護ステーション代表: 横浜がん哲学外来・カフェ代表)で、【基調講演『言葉の処方箋』&『樋野先生へ がん哲学外来の発祥・開港についてのインタビュー』】の機会が与えられた。
『パネルディスカッション:院外で初めて発祥の地・横浜』のパネラーの『初代の横浜がん哲学外来代表』溝口修氏から第1回目の『VIP横浜:がん哲学外来』の開催は2008年9月だったと記憶していますとの心温まるメールを頂いた。
1. 『VIP横浜』でゲストとしてお迎えした樋野先生から声掛けを頂いた後、
2. 第1回目を、『VIP横浜・がん哲学外来』と称して、横浜駅近くのVIP横浜のメンバーの娘さんのマンションの一室で行いました。
3. 2回目は、横浜駅近くのシェラトンホテルの2階のロビーで。そのときに、陣川チヅ子氏(ふれあいの家居宅介護支援ステーション管理者)が参加下さり
4. 3回目から、東神奈川の陣川チヅ子氏の職場の事務所で開催するようになり、その後、中山の糸川幸杞氏(ケアーショップアイ・ティー・オー専務取締役(元横浜がん哲学外来副代表)の眼鏡屋さんの2階で開催するようになりました。
5. 2回目までは、『VIP横浜・がん哲学外来』と称していましたが、樋野先生の提案で『VIP』という冠を外して『横浜・がん哲学外来』になりました。
6. 以降、18年間の『がん哲学外来』の広がりを見ると、この樋野先生の提案は、まさに、将来を見据えた樋野先生の『先見性』であったように思わされています。
以上が、記憶にある18年前のことです。
2月15日は、『日本地域医療連携システム学会』理事長として 京都府宇治市の宇治市産業会館での【第9回『日本地域医療連携システム学会』&市民公開講座 (大会長 京都府立医科大学教授 武藤倫弘先生) 特別講演『心を支えるがん哲学』】の機会が与えられた。 2月16日は、『JSHT Lynch症候群委員会のアドバイザー』として、Zoom ミーティング 『2025年度 第2回Lynch症候群委員会』に参加した。 2月17日 新渡戸稲造記念センターから、順天堂大学医学部医学系研究等倫理委員会に赴いた。『純度の高い専門性と包容力のある倫理委員会』は勉強になった。 今回は、大変貴重な『4連チャン症候群』の日々となった。