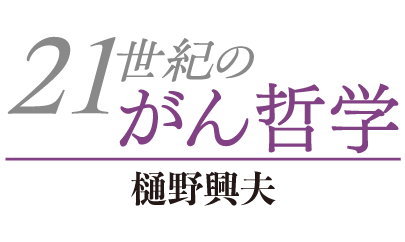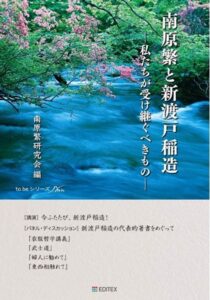第121回 ”対話の場”の必要性 〜 自らの役割が生まれる 〜
2026年2月1日(日曜日) 今年も早、2月を迎えた。 自宅から満月を眺め 心が癒された。『21世紀の懸け橋 〜 “がん哲学” 〜』は、今回で第121回になった。 編集担当の宮原富士子氏が、記念誌として、冊子化を企画される予感がする。
2024年5月6日、2008年 NPO法人『がん哲学外来』設立で お世話になった吉川研一氏、風早謙一郎氏と一般社団法人『がん哲学外来』の事務局の宮原富士子氏、社員の土屋千雅子氏と5人で、東久留米ジョナサンで対談の時を持ったことが、鮮明に思い出された。 大変有意義な時であった。 そして、ブログ『21世紀の懸け橋 〜 “がん哲学” 〜』の発行が決定された。 大いに感服した。
『がん哲学=生物学の法則+人間学の法則』である。 筆者が初めて『がん哲学』を提唱したのは2001年である。 その2年後の2003年、日本病理学会で吉田富三(1903-1973)の生誕100周年記念事業が行われた際、初めて『がん哲学』という言葉を世の中に公表した。
2005年にアスベスト(石綿)による中皮腫や肺がんなどの健康被害が社会問題になったとき、順天堂大学医学部教授時代で 中皮腫の早期診断法を開発していた。 そこで 順天堂大学附属病院で『アスベスト・中皮腫外来』を開設し、問診を担当した。そして、がんと共に生きるこれからの時代において、その不安や心の痛みを受け止め、”すき間”を埋めるための対話が必要だと、病院に提案して『がん哲学外来』を2008年に開設した。 各新聞社で大きく取り上げられ、全国各地から予約が殺到した。 キャンセル待ちも出るほどで、”対話の場”の必要性を確信したものである。
『がん哲学外来』には、多くの患者さんが来られた。 困っている人のために居場所を作る。 それが人間としての使命であろう! 【『病気』であっても『病人』ではない社会】は、人類の進む方向である。 新渡戸稲造(1862-1933)の言葉に『人生に逆境も順境もない』とある。【 自分のことばかり考えると、悩みや苦しみが 立ちはだかって逆境になる。でも、自分よりも困った人に手を差し伸べようとすれば、自らの役割が生まれ、逆境はむしろ順境になる。】
第120回 『時空を超えて 受け継ぐべきもの』 〜 『自由にして勇気ある行動』 〜
2026年1月24日の2周年記念『第25回小岩メデイカルカフェ みちくさ』(江戸川区 小岩栄光キリスト教会に於いて)に参加された方から、【今、『南原繁と新渡戸稲造 〜 私たちが受け継ぐべきもの 〜』(
筆者は、島根県出雲大社町鵜峠(現在は人口約30名、空き家60%)に生まれ、鵜鷺小学校(現在は廃校)の卒業式で、来賓が話された【『ボーイズ・ビー・アンビシャス』(boys be ambitious)(1877年札幌農学校のクラーク(1826-1886)の言葉)が胸に染み入り、希望が灯るような思いを受けた】。 人生の起点である。 札幌農学校におけるクラーク精神が、内村鑑三(1861-1930)と新渡戸稲造(1862-1933)へと導かれ、そして、南原繁(1889-1974)と 矢内原忠雄(1893-1961)へと繋がって行った。 筆者の読書遍歴は『内村鑑三・新渡戸稲造・南原繁・矢内原忠雄』である。
筆者は、2004年にスタートした南原繁研究会【初代代表、鴨下重彦 先生(1934年-2011年、東京大学名誉教授、国立国際医療センター名誉総長)、第2代代表、加藤節 先生(成蹊大学名誉教授)】の3代目の代表を2019年 南原繁(1889-1974)生誕130周年を祝し仰せつかった。南原繁は、内村鑑三と新渡戸稲造から大きな影響を受けた。 【南原繁は『教養ある人間とは、自分のあらゆる行動に普遍性の烙印を押すことであり、自己の特殊性を放棄して普遍的な原則に従って行為する人間のことである』&『それは人間の直接的な衝動や熱情によって行動する代りに、つねに理論的な態度をとるように訓練されることである。』(南原繁著作集第三巻)& 『時代を動かすリーダーの清々しい胆力』としての『人間の知恵と洞察とともに、自由にして勇気ある行動』(南原繁著の『新渡戸稲造先生』より)『練られた品性と綽々たる余裕』は『教育の真髄』であり『ビジョン』は人知・思いを超えて進展する】という文章が思い出される日々である。
将棋棋士 加藤 一二三氏(1940年1月1日 – 2026年1月22日)が、86歳で、ご逝去されたとのことである。 2022年の『新渡戸稲造生誕160周年記念』で、一緒に講演の機会が与えられたことが、今回、鮮明に想い出された。(添付)